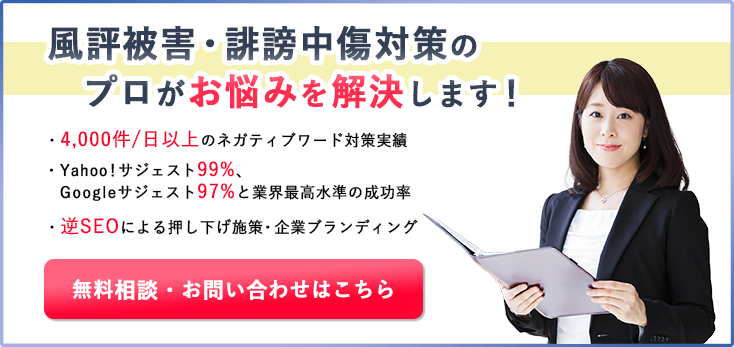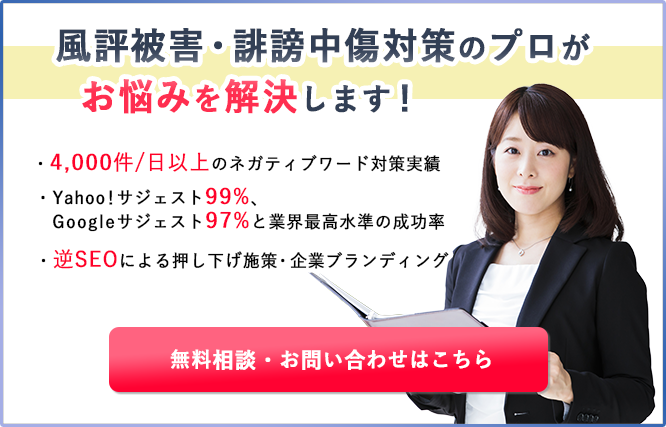本稿では改めて店舗のレピュテーションリスクとその管理について考えてみましょう。
当サイトの記事を読んでいただいている方々には今更という部分もあるかと思いますが、ここで改めてレピュテーションリスクについてしっかりと理解し、イメージの形成とリスク回避に役立てていただければと思います。
レピュテーションリスクとは
レピュテーションが企業や店舗の評判を意味していることは広く周知されている所です。
レピュテーションリスクとは事実無根の風評や不用意な言動により店舗が負うリスク(危険)の事を意味しています。
昨今では「アルバイトが悪ふざけをしている動画をSNSにアップした」「従業員が内部情報を漏らした」といった事でレピュテーションリスクが顕在化。それがSNSや口コミを通じて広く拡散されていく事で店舗の信頼は失墜し、経営に大きなダメージを与えるといった流れが増えています。
評判・信用は築き上げるのが大変な反面、崩れ去る時は一瞬なので、このリスクをどう回避していくかが非常に重要になってきます。
食事の味を上げることやサービス品質の向上だけでなく、そこで獲得した評価や信頼をどのように維持するかを考えることが店舗のレピュテーションリスク管理には欠かせません。
過去の記事から、レピュテーションリスクを回避できなかった為に企業イメージに深刻な影響を受けた例を見てみましょう。
[myphp file=’cvbtn_fuhyo’]
レピュテーションリスクを回避できなかった2つの事例
事例1:センチュリー21
[blogcard url=”https://fuhyohigai-college.com/century21/”]
2016年に起こったセンチュリー21での炎上事例です。
不動産仲介業界の中でも最大手の企業が起こした事件として当時は取り上げられました。
芸能人が部屋を借りに来た事、どのようなマンションに住もうとしているかなどを従業員がSNSでつぶやいたことで大きな問題に発展したこの事件。
メディアや報道機関で扱われるに至り、雇用主であるセンチュリー21が失った信用は取り戻すのに相応の時間を要します。
事例2:ブロンコビリー
[blogcard url=”https://fuhyohigai-college.com/parttimejob/”]
2013年と既に過去の話ではありますが、いまだ検索するとその話題が出てくることから当時世間に与えた影響は大きなものがありました。
学生アルバイトが業務用冷蔵庫に入り込んだ写真をTwitterにアップしたことから大きな問題へと発展したこの事件。
当該店舗は閉店に追い込まれるなど自体は深刻なものとなりました。
レピュテーションリスク回避のために
上記2点を見てみると、どちらも従業員・アルバイトのネットリテラシーが欠けていることが事件の原因となっています。
昨今は従業員のネットリテラシー教育が企業のレピュテーションリスクの管理として重要となっており、既に何らかの方法で導入している企業も多いのではないかと思います。
しかし、もしまだ規定が整備されていない場合は早急に対応を進める必要があります。
店内やアルバイト中のスマホの使用可否、万が一の場合の責任の所在などを規定に盛り込み従業員との相互理解を深めるといったことが重要です。
もちろんこれだけがレピュテーションリスクの管理における問題点ではありませんが、特に顕在化しやすく店舗に与えるダメージが多い箇所から順次対応を行っていきましょう。
まとめ
レピュテーションリスクとその管理の重要性についてはご理解いただけたでしょうか。
ネット使用者の若年層化に伴い、これからも同様の事件が起きる可能性は否定できません。
自店舗が被害に遭わない為にも、この記事を『規約に足りていない点は何か』を見つめなおす一助としていただければと思います。